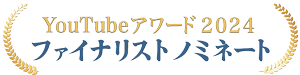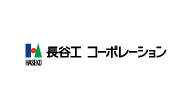近年、インターネット環境の進化やスマートフォンの普及により、動画は私たちの生活にますます身近な存在となりました。こうした時代の中で、テキストや画像だけでは伝えきれない多くの情報を効率的に届けることができる動画は、企業が自社や商品の魅力を発信するための重要なPR手法となっています。
そこで本記事では、PR動画の制作方法や制作時に押さえておきたいポイント、費用相場や成功事例まで詳しくご紹介します。
動画を活用した効果的なPR戦略を知り、自社の魅力を最大限に引き出す動画作りにチャレンジしてみませんか?
また、プルークスでは、動画制作・映像制作、縦型ショートドラマ、ショート動画運用など、様々なコンテンツに役立つ限定ダウンロード資料をご用意しています。実践に活かせる事例とノウハウが詰まったコンテンツをぜひご活用ください。
PR動画とは
PR動画とは、企業や団体が自分たちの商品やサービス、ブランドなどをPRする目的で制作した動画のことです。
それまでのテキストや画像による情報発信と比べて、動画は情報量がとても多く、複雑な内容も分かりやすく伝えることができます。そのため、記憶に残りやすく、共感や興味を引きやすいといった理由から、効果的なプロモーション手段として注目されています。
最近では、YouTubeやTikTok、Instagramなど、数多くの動画配信プラットフォームの普及が進み、動画コンテンツは、性別や年齢を問わず、幅広い層にリーチできる点が大きな魅力になっています。また、動画配信プラットフォーム以外でも、企業のホームページやSNS、リアルイベントなど、あらゆる場面で効果的に活用されています。
PR動画の活用シーン


PR動画は、商品・サービス紹介、企業ブランディング、店舗・観光施設紹介、イベント・展示会、営業活動、採用活動など、多岐にわたるシーンで活用されています。
では、それぞれについて詳しく見てみましょう。
商品・サービス紹介
PR動画のもっとも一般的な活用方法は、自社の商品やサービスの紹介です。今までのチラシやホームページでは、写真や文章、キャッチコピーで商品の良さをアピールすることしかできませんでした。しかし、動画を利用することで、商品やサービスをより詳しく、わかりやすく伝えることができます。
文章や静止画だけではどうしても伝えにくい、商品のもつ質感や動きも、動画であればよりビジュアルとして見た人にアピールすることができます。また、説明するのが難しい商品や仕様も、アニメーションや実演映像を交えることで、わかりやすく伝えることができます。
商品を実際に使ったことがある利用者のコメントを動画に加えれば、信頼性を高める効果も生まれ、より商品やサービスのPRに貢献できます。
企業のブランディング
企業のブランディングのためのPR動画は、企業が目指す理念やビジョン、社会的価値などを伝えて、企業のイメージアップを狙うものです。企業にとってブランドイメージは非常に重要ですので、ブランディング動画のクオリティが企業価値に直結すると言っても過言ではないでしょう。
心に響くメッセージや感情に訴えかけるストーリーを通じて、企業の「人間らしさ」や「社会的責任」を表現したり、美しい映像表現や迫力あるBGM、スタイリッシュな構図などを活用して企業の将来性やアクティブさを演出したりと、それぞれの企業イメージを効果的に表現する、魅力的な動画が多く制作されています。
また、動画の長さに制限がなければ、企業の歴史や文化、社員の働き方CSRへの取り組みなどをじっくりと見せる動画を制作することで、クライアントやユーザー、就職希望者などに企業のより深い個性を印象づけることができます。
店舗・観光施設紹介
最近では、外国人観光客も増加し、観光業界は日本経済において重要な役割を果たしているといえるでしょう。観光客が増えることで、地域経済が豊かになり、雇用創出や地方創生にも貢献しています。
日本語がわからない外国人観光客向けに、お店や観光施設を紹介するために、動画は特に欠かせないツールです。
動画では、ホテルの客室やレストラン、観光地の美しい景色やアクティビティをダイレクトに見る人に伝えることができます。また、施設の使い方やアクセスなど、実用的な情報も盛り込んでおくと、訪れる人の不安をやわらげることができます。動画は1本だけではなく、さまざまな角度で、季節やイベントごとに制作することで、リピーターを生む効果も期待できます。
イベント・展示会
イベントや展示会のPR動画は、イベント開催前の告知とイベント開催後のアーカイブという2つの役割があります。
イベント開催前に制作する動画の目的は、もちろん来場促進です。この動画では、イベントの概要や出展者情報、見どころなどを紹介し、動画を見た人に「行ってみよう」と思わせなければなりません。
一方で、イベント開催後に制作する動画は、会場の盛況ぶりや参加者の声、ハイライトシーンなどをまとめた記録目的のものになります。このイベントの様子をまとめた動画は、参加できなかった人に「行けばよかった」と思わせて、次回以降の集客につなげることが大切です。さらに、出展者やスポンサーにとっても、自社の参加実績をPRする営業ツールとして使えるという効果もあります。
営業活動
最近では、企業が営業活動のツールの一つとして、PR動画を積極的に活用しています。
営業担当がクライアントに対して口頭で説明だけでは伝わりにくい部分を、動画を使って視覚的に伝えることで、クライアントの理解を深めることができます。また、重要なことを動画にいれておけば、後になって「聞いてない」と言われるリスクを減らすことにもつながります。
営業担当が実際に訪問する前に、PR動画のリンクを共有しておくことで、商談にかける時間を少なくすることにもつながります。効果的にPR動画を拡散することで、今までは直接商談することが難しかった遠方の潜在顧客や海外のクライアントへのアプローチも容易になります。
このようにPR動画は営業活動において、非常に力を発揮するツールと言えます。
採用活動
採用活動のためのPR動画は、その企業の魅力や社風、職場環境を就職希望者に効果的に伝えることができます。
就職や転職を検討している人が本当に知りたいのは、その会社の実際の雰囲気や社員たちの働く姿、働く人の声です。このようなことは文字情報だけでは伝わりにくいため、動画で見せることはとても効果があります。企業のオフィスツアー動画や若手社員のインタビュー動画など、実際の勤務環境をイメージしやすい動画を取り入れることで、就職希望者の不安を解消できます。
特に最近の若い人は、テキストよりもYouTubeなどの動画サイトで情報を収集する傾向があるため、採用動画があると、新卒や若手の就職希望者に届きやすくなります。さらに、SNSで効果的に拡散にすれば、少ないコストで採用活動を行うこともできます。
PR動画を制作するメリット
PR動画は、高い情報伝達力や視覚的訴求力、感情的訴求力など、表現力に関するメリットに加え、拡散性や多言語対応などの具体的なメリットも多くあります。ここでは、その中でも特に大きな利点について、詳細を説明します。
記憶に残りやすい
ハッと驚くような映像や耳に残るフレーズ、共感性が高いストーリーは、見た人に深い印象を与え、長期的な記憶へとつながります。これは人間の脳は、文字だけの情報よりも、視覚や聴覚を活用した映像と音声を組み合わせた情報のほうが定着しやすいためです。
動画の反響はすぐに出るものもあれば、すぐには出ないものもあります。手ごたえがないとそのまま動画を使わなくなったり、制作を継続しないという判断もでてくるでしょう。
しかし、すぐに反応がなかったとしても、長期的な記憶としてその商品や企業がインプットされていると、何かのタイミングで購入につながったり、好意的な印象を抱いてくれます。しっかりと受け手に届くようなクオリティのPR動画を制作することが大切です。
拡散が期待できる
PR動画は、YouTubeやInstagram、TikTokなどの拡散力の高いメディアに投稿することで、面白いと感じた視聴者が動画をシェアして、自然に拡散されます。なるべく「バズる」ような動画を制作して、狙い通りにうまく拡散されれば、コストをかけずに多くの人に見てもらうことができます。逆にコストをいくらかけても、中身がともなわなければ話題にはなりません。
特に、若い世代は面白いことに対する感度も高く、SNSを駆使して情報共有を積極的に行うため、若年層をターゲットにした商品やサービスのPRには動画が非常に有効です。また、動画の内容によっては、インフルエンサーによる紹介や、まとめサイトでの紹介といった、二次的な拡散も期待できます。
多言語に対応できる
動画は、いろんな国の言葉で吹き替えたり、字幕をつけたり多言語に簡単に対応することができます。それに加えて、動画のメッセージは言葉の壁を超えて、ボーダレスにメッセージを伝えるパワーがあります。私たちも海外の動画を見て、言葉やテキストがわからなくても、面白いと感じたり、美しいと共感することがあるでしょう。
多言語に対応した動画があれば、海外の人に企業や商品を知ってもらうきっかけになり、ビジネスの可能性が広がります。特に観光業や輸出業など、海外との関わりが深い企業は、現地の言葉で情報を発信することで、相手に親近感や安心感を与えることができます。
何度も繰り返し視聴できる
展示会などのイベントでチラシやパンフレットを配布する場合、数がなくなったらすぐに新しいものを準備しなければいけません。そのたびにコストも手間もかかります。
しかし、動画の場合はQRコードを活用することで、それぞれのスマホやパソコンで簡単にアクセスでき、リアルタイムで再生して見てもらうことができます。チラシやパンフレットを用意する必要もなく、コストを抑えつつ効率的に多くの人にアプローチできます。
このように、PR動画は一度制作すれば、同じクオリティで、何度でも同じ内容を届けることができて、長期間にわたって活用することができるのが魅力です。繰り返し使えるという点も非常に効率的で、コストがかからないツールになっています。
編集がしやすい
動画は素材さえあれば、編集次第で色々な使い方をすることができます。編集によって10分の動画から30秒のダイジェスト版を作成したり、一部の解説部分を抜き出してハウツー動画に加工することもできます。また、ハイライトシーンを厳選し、迫力のあるBGMを重ねることで、イベント会場向けの動画として再編集することもできます。
以前は動画編集はプロに頼まなければいけない難しいものでしたが、最近では誰でも使える動画編集ソフトも数多く販売されています。クライアントによって少しずつ動画の中身を変えたり、情報をアップデートするくらいなら難しくはありません。SNS投稿用、展示会用、商談用など、その用途にあわせてPR動画をアレンジすることをおすすめします。
低コストでスタートできる
テレビのCMのように有名人を起用して、多額の制作費用をかけた動画もありますが、基本的に動画は限られたコストでも制作することができます。InstagramやTikTokを見てみると、普通の人が作った動画が人気を集めて、たくさん拡散されていたりします。
PR動画は多額のお金をかけたからよいというわけではなく、ターゲットの心に届く動画を作ることが大切です。動画制作ソフトを学んで、自社で制作する場合でも、ある程度魅力的な動画を作ることはできます。しかし、より早く、自分たちの満足するPR動画を制作するためには、プロのサポートを受けることが必要です。動画制作の費用対効果をしっかり検討して、自社にあった制作プランをたてましょう。
効果測定ができる
マーケティング効果を数値で測定しやすい点も、PR動画のメリットのひとつです。
例えば、チラシを配布した場合、商品の売り上げの変動などで大まかな効果を測定することはできますが、どれだけの人が見てくれたか、訪問につながったかを詳細に知ることは困難です。
しかし、PR動画の場合は、再生回数、視聴継続率、エンゲージメント率(いいね、コメント、シェア数)などの指標を通じて、どの程度見た人の関心を引いたかを正確に把握することができます。
また、複数のバージョンの動画を制作して効果を比較検証するABテストを実施して、よりパフォーマンスをあげる検討をすることもできます。視聴者の属性分析、視聴デバイス、視聴時間帯などの詳細データを活用することで、自社のマーケティングデータを取得することができます。
PR動画の作り方
PR動画の制作は、大きく分けて「ターゲット設定」「コンセプト・構成の策定」「撮影」「編集」の4つのステップで進められます。
それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
ターゲット設定
PR動画を制作する前に、動画のターゲットを設定することはとても重要です。このターゲットがずれてしまうと、動画を見た人から期待通りの反応を引き出すのが難しくなってしまいます。
ターゲットの年齢、性別、職業、興味関心などを具体的に設定することで、ターゲットに強く響く動画コンテンツを制作することができます。
ここで注意してもらいたいのは、ターゲットを広く設定しないようにすることです。たくさんの人に届けたいという気持ちが強いと、欲張って広いターゲットを想定してしまい、結果的に誰にも響かないぼやけたPR動画になってしまう可能性があります。絞り込んだターゲットのニーズや課題を把握することで、ターゲットに役立つ情報や共感を得られるストーリーを盛り込むことができます。
コンセプト・構成の策定
ターゲットを設定したら、次は動画のコンセプトや構成を決定します。まずは、「ターゲットにどのような感情を持ってもらいたいか」「どのような行動を促したいか」という目的とコンセプトを明確にします。
ターゲットやコンセプトが決まったら、それに沿ったストーリーや構成を作っていきます。「ターゲットの関心を引く導入部」→「メインメッセージ」→「具体的な行動を促すエンディング」といった流れが一般的です。同時に、動画の長さやテンポ、音楽、効果音なども考慮して、視聴者につまらないと思わせない魅力的な構成を工夫しましょう。
特に冒頭の数秒間は、視聴継続を左右する重要なポイントになります。インパクトのある映像や問いかけで興味を引くことで、離脱を防ぐことができます。
撮影
いよいよ動画撮影の段階に入ります。しかし撮影自体よりも、撮影前の準備が実はとても重要です。撮影する場所、撮影許可の手配や、出演者の選定など、決めなければならないことがたくさんあります。なるべく細かい絵コンテやショットリストを作成して、必要な機材や人を漏れなく手配するよう心がけましょう。
撮影中は、編集作業で使用する素材として、同じシーンを複数のアングルから撮影したり、つなぎ用のショットを意識的に収録すると、編集時に役立ちます。
高いクオリティの動画を制作するには、プロのカメラマンやディレクター、プロ用の機材が必要になるでしょう。ただし、予算に応じてスマートフォンと三脚で撮影することも可能です。
編集
撮影した映像は、編集ソフトを使用し、カットの調整やシーンのつなぎ合わせ、テロップやBGMの挿入、効果音の追加などの加工を行います。
映像や音声の品質に注意し、見た人が「見えにくい」「聞こえにくい」と感じないような動画制作を心掛けましょう。また、せっかく撮影した動画だからといって、不要なシーンを削るのをためらうと、冗長で間延びした動画になってしまうことがあります。情報を詰め込みすぎず、テンポよく構成し、視聴者の興味を維持することが大切です。
さらに、アニメーションやCG映像を加えたり、既存の映像に合成することで、表現の幅を広げることができます。撮影が難しい場合や、より抽象的な表現を求める場合は、イラストレーターやアニメーション制作ソフトを活用し、アニメーションや画像のみの動画を制作するのもひとつの方法です。
PR動画の活用方法


PR動画は、WebサイトやSNS、実店舗や展示会での放映など、様々な媒体で活用できます。それぞれの媒体ごとの特徴をしっかり理解して、動画配信のパフォーマンスをあげることが大切です。
Webサイト・LP(ランディングページ)
商品やサービスを紹介するWebサイトやLPに動画を埋め込むことで、文字だけでは伝わりにくい商品の特徴や使用感、企業の雰囲気などを視覚的に伝えることできます。その結果、見た人が「購入」「資料請求」「申し込み」などの具体的なアクションをおこして、コンバージョン率の向上に大きく貢献します。
また、最近ではユーザーのサイト滞在時間もGoogleのサイト評価の大きなポイントになっています。動画があることで、ユーザーのサイト滞在時間が延びると言われているため、SEOの効果も期待できます。ただし、あまり重たい動画を挿入すると、サイトの表示に時間がかかって、ユーザーの離脱にもつながるため、動画の尺には注意が必要です。
SNS
動画はSNSとの相性がよく、もっとも効果を発揮するため、PR動画をできるだけ多くの人に見てもらうには、SNSへの投稿が有効です。ターゲット層がよく利用するSNSを選んで動画を投稿することで、ターゲット層を中心に広く拡散することができます。
若者向けのSNSといわれるInstagramやTikTokは、動画の長さが1分程度と短く、縦長のスマートフォンでの視聴を前提としています。タイムラインには、たくさんの動画が流れていくので、より瞬間的に面白いと思わせる工夫が必要です。
YouTubeでも、ショート動画は増えていますが、15分以上の長い動画でも視聴される傾向にあるので、より詳しい情報を盛り込んだ長めの動画も効果的です。また、FacebookやTwitterで自動再生される点を考慮し、音声がなくても内容が伝わるように字幕やテロップを作っておくのも大切です。
広告
PR動画は、Web広告として出稿することで、より多くの人にリーチし、認知度の向上や購買促進につなげることができます。
Web広告には、大きく分けて「不特定多数に配信する広告」と「ターゲットを絞って配信する広告」があります。不特定多数に向けた広告の代表例としては、YouTubeのインストリーム広告があり、視聴者が検索して視聴する動画の冒頭や途中に表示されることで幅広い視聴者にアプローチできます。
一方、ターゲットを絞って配信する広告としては、FacebookやInstagramのフィード広告が挙げられます。ユーザーの興味関心や閲覧履歴に基づいて配信されるため、より関心の高い層にリーチしやすく、効率的なプロモーションが可能です。
デジタルサイネージ
街中やショッピングモールなどに、大きなモニターやテレビを使って動画を流す仕組みのことをデジタルサイネージと言います。最近では、電車の中やオフィスビルのエレベーター内など、人の流れがある場所にたくさん設置されています。
デジタルサイネージ向けの動画は、音声が流れないことも多いため、字幕やビジュアル中心の構成にすることが重要です。また、行きかう人に足を止めて見てもらえるような印象に残るビジュアルインパクトを作らなければいけません。長時間見てもらうことはできないので、15〜30秒程度の短いコンテンツに、ワンメッセージを効果的に伝える動画を制作しましょう。
展示会・イベント
動画は商品のデモンストレーションやサービスの特徴をダイレクトに映像で伝えることができるので、展示会やイベントの場でも活用されています。
ブースに設置したモニターでPR動画を流しておくと、遠くからでも来場者の目を引き、足を止めてもらうきっかけになります。また、ブーススタッフが対応できる人数には限りがあるため、説明する人がおらず、興味を持った人を逃してしまう機会損失を防ぐという効果もあります。
展示会で配布する名刺やパンフレットに動画のQRコードやURLをいれておくことも大切です。イベントが終わった後で、気になった人はアクセスして、見てくれる可能性もあります。また、イベント用に動画のURLを変えておけば、そこからアクセスしてくれた人数を知ることもできます。
メール
年齢が高めの人はSNSはあまり利用せずに、メールを利用している人も多いので、ターゲットの年齢層が高い場合はメールが効果を発揮します。PR動画をメールマガジンなどにはりつけて、ユーザーに届けましょう。
この場合、メール内に動画を埋め込むとデータ量が大きくなってしまうため、サムネイル画像と再生ボタンを配置し、クリックするとWebサイトやランディングページにアクセスする、という方法が一般的です。
メールアドレスを知っているということは、既存顧客や潜在顧客である場合が多くなります。メールの場合は拡散はあまり期待できませんが、それを逆手にとって会員限定、お得意様限定のPR動画を制作して配信すると、高い効果が期待できるでしょう。
PR動画制作のポイント
ここでは、PR動画の効果を最大限に発揮させるために、制作時に意識するとよいポイントをご紹介します。
ターゲット層の潜在ニーズを把握する
ターゲット層の年齢、性別、興味関心などを分析し、ターゲット層が求める情報を動画に取り入れましょう。この時、表面的なニーズだけでなく本質の部分を探ることが重要です。
例えば、ある商品を購入したいと思う背景には、「便利さが欲しい」だけでなく、「時間に余裕が欲しい」「周りから認められたい」といった深い思いがあるものです。こうした本音の部分を把握するには、アンケートだけでなく、日常の会話やSNSでの反応なども参考になります。
ターゲットの表面的な要望だけでなく、心の奥にある願いに応える内容を盛り込むことで、より深い共感を呼ぶ動画を制作することができます。
冒頭で視聴者を惹きつける
動画の冒頭で視聴者の興味を引く工夫をしましょう。冒頭で視聴者を惹きつけることで、視聴離脱を防ぐことができます。特にSNSや広告での活用を考える場合、最初の3〜5秒で視聴者に「続きを見たい」と思わせる演出が必要です。
そのためには、「インパクトのある映像や音楽を使用する」、「ターゲット層の関心事を直接提示する」、「興味を引く問いかけを行う」などの工夫が有効です。その際、ターゲット層の関心や価値観を十分に理解することが重要です。
ストーリーで共感を呼ぶ
PR動画にストーリー性を取り入れることで、視聴者の共感を得やすくなります。単に商品やサービスの特徴を伝えるだけでなく、共感できるストーリーを展開することで、感情に訴えかける動画に仕上がります。特に、実際のユーザーの体験談や、視聴者にも起こり得る日常の一場面を切り取ったエピソードなどは、強い共感を生み出します。
また、ストーリーの主人公は、視聴者が自分を投影できる存在であることが望ましいです。「自分もこんな経験がある」「自分だったらどうするだろう」と感じられるような内容にすることで、商品やサービスへの親近感が生まれ、記憶に残る動画となります。
使用目的に合った長さにする
PR動画の長さは、視聴者の集中力や視聴環境に大きく影響します。特に、スマートフォンでの視聴が主流となる媒体では、短くテンポの良い動画が好まれます。一方で、長尺の動画が必要な場合は、チャプター分けや目次の表示など、視聴者が必要な情報にアクセスしやすい工夫を施すことで、最後まで視聴してもらえる可能性が高まります。
一般的に、SNS向けは15〜60秒、Webサイト掲載用は1〜3分、詳細な商品説明やブランドストーリーは3〜5分程度が目安です。
音楽や効果音を活用する
動画において音楽や効果音は、視聴者の感情や印象に大きく影響を与えます。映像にあった音楽を使用することで、メッセージの伝達力を高めたり、ブランドイメージを強く印象付けたりすることができます。また、効果音は視聴者の注意を引き、重要なポイントを強調する役割を果たします。
音楽を選ぶ際は、ターゲット層の好みや動画の目的に合った楽曲を選ぶことが重要です。例えば、クラシック音楽を用いることで高級感を演出したり、人気のあるミュージシャンとのタイアップを活用することも効果的です。
一貫したブランディング
PR動画は、ブランドの認知度を高めるための重要なツールです。動画の中でブランドの要素を統一するよう心がけましょう。例えば、企業ロゴを適切に配置したり、ブランドカラーを統一して使ったり、フォントや画面のデザインを揃えたりすることで、視聴者に一貫した印象を与えることができます。こうした工夫により、視聴者は無意識のうちにブランドを覚えやすくなります。
また、動画の「話し方」や「表現のスタイル」も統一することが重要です。たとえば、普段は親しみやすいイメージのブランドが、突然かたい言葉遣いをすると、視聴者に違和感を与えてしまうことがあります。さらに、PR動画だけでなく、他の広告やプロモーション企画、マーケティング施策ともメッセージを統一することで、ブランドのイメージをより強く印象づけることができるでしょう。
PR動画制作を外注する際の注意点


動画制作会社の選定は、動画制作を成功に導くための大きな要素のひとつです。では、外注で高品質で大きな効果が期待できる動画を制作するには、どのような制作会社に依頼すればよいでしょうか。
制作会社の実績と相性
制作会社によって、得意な動画の種類やデザインが異なります。過去のポートフォリオを確認し、自社のイメージや目的に合った動画を制作できる制作会社を選びましょう。過去の制作実績やポートフォリオを確認することで、制作会社の得意分野を把握することができます。
また、制作物だけではなく、担当者の姿勢も大事です。打ち合わせ時の対応や提案内容、コミュニケーションの円滑さなど、相性の良さも重要な判断基準です。こちらの意図をしっかりと理解し、修正依頼にも柔軟に対応してくれる制作会社を選ぶことが大切です。
予算とクオリティのバランス
PR動画の制作費は、制作会社によってかなり異なります。まずは複数の制作会社から見積もりを取り、費用や納期を比較検討するとよいでしょう。また、見積もり上は安く見えても、修正や編集に追加料金が発生する条件などもありますので、事前に確認しておくと安心です。
動画のクオリティは、かけられる費用によって大きく変わってきます。費用を抑えることにこだわりすぎると、品質が下がってしまう可能性もあります。そうは言っても、予算をかければかけるだけよい、というものでもありません。そうならないためには、「派手な演出よりメッセージの明確さを優先したい」など、自分たちの優先順位を明確にし、制作会社と共有しておくことが重要です。
契約内容と権利関係の確認
動画は作った後も、さまざまな用途で活用できるため、制作会社と権利関係でトラブルになることがあります。動画制作を外注した場合、その動画の著作権は制作会社に帰属することが一般的です。したがって、会社のウェブサイトでの使用を前提に制作された動画を、納品後に許可なくSNSや他の動画共有サイトにアップロードしたり、クリエイターに無断で加工したり、気軽にカスタマイズしてしまうと、契約違反となる場合があります。
発注者が動画をどのように利用できるかは、事前に制作会社と取り決めておく必要があります。もし、永続的に利用したい場合は、著作権を移転するような契約を結ばなければなりませんが、その分費用は高くなります。これらのトラブルを避けるためには、契約を結ぶ前に契約書の内容をしっかりと確認し、動画の利用範囲や権利関係について制作会社と十分に話し合っておくことが重要です。
PR動画制作の費用
PR動画の制作費用は、品質や内容、プランによって大きく異なります。フリー素材を活用したスライドショー形式の動画や、過去に撮影した映像を使用したベーシックなタイプの動画であれば10万円程度で制作可能ですが、本格的な撮影が必要なものは100万円以上かかるのが一般的です。
以下は、おおよそのPR動画の制作費用です。
| 動画の種類 | おおよその費用 |
| スライドショー形式の動画 | 10~30万円 |
| 社内風景や社員インタビュー | 30~150万円 |
| 商品・サービス紹介動画 | 50万〜200万円 |
| 役者が出演する実写 | 150万円〜300万円 |
| CGを使ったアニメーション動画 | 200万円以上 |
PR動画制作の事例
ここでは、弊社プルークスが制作したPR動画の中から、効果的な動画制作の参考になる事例をいくつかご紹介します。
日本高圧コンクリート株式会社様
日本高圧コンクリート株式会社様の採用向け会社PR動画です。力強いパーカッションのリズムに乗せて、メッセージを大きく大胆にみせることで、視聴者の興味を引きつけ、全国のインフラを支える企業の力強さを表現しています。
写真やイラスト、テキストをテンポよく配置し、企業の歴史や業務内容を感覚的に理解できる形で解説することで、就職後の自分のイメージが想像できるように工夫しています。
東北電力株式会社様
東北電力株式会社様のブランドPR映像では、東日本大震災を題材にして、心に響く映像作品を制作しています。動画では、実際の被災地の写真と、被災地で懸命に活動する人々の姿を描いた映像を織り交ぜながら、人々が支え合いながら働くことの意義や、困難を乗り越え未来に希望を見出す姿を通して、企業が社会と真摯に向き合う姿勢を伝えています。
【CM】東北電力株式会社_ブランディング映像(PROOX制作実績)
株式会社groove agent様
不動産仲介・リノベーション設計を行う株式会社groove agent様が開催しているリノベーションセミナーのPR動画。最初に「家を買うの、ちょっとストップ」という、家の購入を検討している視聴者の心にストレートに響くメッセージを提示し、視聴離脱を防ぐ工夫が施されています。その後も、家の購入に伴う不安点を具体的にあげ、視聴者の共感を得ながら、その解決策として、スムーズにセミナーへと誘導しています。
【WebCM】株式会社groove agent様_セミナーPR映像(PROOX制作実績)
any株式会社様
企業内で情報やナレッジを共有・活用するためのクラウドサービスを提供する、any株式会社様のサービス紹介動画です。仕事上の具体的な悩みをいくつか挙げ、それらをスムーズに解決する手段として自社サービスを紹介しています。この流れにより、視聴者は自分が抱えている問題の解決をイメージしやすくなります。また、実際の画面を表示しながらサービス内容を説明することで、サービス導入による作業効率の向上を疑似体験できる構成になっています。
【サービス紹介】any株式会社様_「Qast」PR映像(PROOX制作実績)
株式会社マイナビミドルシニア様
株式会社マイナビミドルシニア様が運営する、40〜60代に特化した求人サイト「マイナビミドルシニア」のCM動画です。職場でのちょっとした勘違いから生まれるコミカルなシチュエーションが楽しめるショートドラマ仕立てです。笑いの中にも、「シニア世代は企業で必要とされている」というメッセージを込めつつ、転職による新たな未来が想像できる動画になっています。
【TVCM】株式会社マイナビミドルシニア様_サービス紹介動画(PROOX制作実績)
まとめ
PR動画は、企業の魅力を視覚的に伝え、認知度の向上やブランディングに効果的なツールです。ターゲット層が好むプラットフォームやスタイル、ニーズを理解し、共感を呼ぶコンテンツを制作することで、知名度やブランド力を想像以上の規模やスピードで広げることも可能です。
デジタル環境の進化に伴い、動画コンテンツの重要性は今後もさらに高まっていくことが予想されます。PR動画を活用し、企業の魅力を最大限にアピールしましょう。