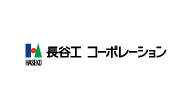従業員教育のために行う「研修」は、企業にとって負担の大きい業務の一つです。そのため外部に委託したり講師を招いたりする企業が多いですが、近年では研修の合理化・均一化を目的としていることや、コロナ禍によって集合研修の開催が難しいため、対策として研修動画を制作する企業が増えています。
今回は、従業員の研修を合理化できる「研修動画」の概要や研修を動画化するメリットや研修を成功させるための動画の作り方、実際に企業が導入した研修動画の事例など、詳しく解説します。
また、プルークスでは、動画制作・映像制作、縦型ショートドラマ、ショート動画運用など、様々なコンテンツに役立つ限定ダウンロード資料をご用意しています。実践に活かせる事例とノウハウが詰まったコンテンツをぜひご活用ください。
目次
研修動画とは
研修動画とは、種類は多岐に渡りますが、録画したものや、セミナー、スピーチをそのまま撮影したものなど、研修に用いられる動画のことを指します。研修の質を均一化できるほか、繰り返し使用できる、会場の準備や研修講師の手配などが不要になるといったメリットもあります。参加者側も同じ時間に同じ場所に集まる必要がなく、都合の良い時間と場所で視聴できるため、研修の参加率の向上が期待できるでしょう。
近年では、コロナの影響によっても研修動画がより注目されるようになっています。理由としては、従来の研修のあり方である、特定の場所に集まって受講することが難しくなり、テレワークの普及に伴って自宅で動画を視聴できる環境が整いつつあるからです。研修動画はオンラインセミナーと並び、新たな研修のあり方として注目されています。
研修に動画を活用する「企業側」のメリット
研修に関連する業務の合理化や研修の効率化が期待できる研修動画ですが、企業が活用することでどのようなメリットを得られるのでしょうか。ここからは、企業が研修動画を導入するメリットについて紹介します。
研修実施のコストを削減できる
従業員を集めて講義形式で行う研修の場合、多額のコストが発生します。発生するコストの具体例は、以下の通りです。
- 研修会場の費用
- 研修講師の費用
- 研修会場までの従業員の交通費
- 研修を開催するための諸経費
研修講師や会場の確保などに必要な従業員の負担を考慮すると、従来型の研修には大きなコストがかかっていることがわかります。一方で研修動画は録画した動画を研修に利用するため、導入すれば毎回かかっていた研修費用を削減できます。また、研修内容が変わらない限り何度でも繰り返し視聴できるため、ほとんど費用がかかりません。
例えば、毎年行われる新入社員へのOJTや研修に使用すれば、新人教育業務の効率化や新人教育にかかる費用を削減できます。
内容をより正確に理解してもらえる
研修に動画を活用すると、従業員に内容を正確に理解してもらえます。理解できない箇所や聞き逃した部分を繰り返し視聴できるため、従来の研修では理解が困難であった内容も理解してもらえるでしょう。なお、現場の様子を再現できるというメリットもあります。動画で現場の様子を視聴することで、従業員は業務に対する理解が深まるでしょう。
また、研修には事前に撮影した動画を使用するため、講師の良し悪しに左右されることもありません。毎回同じ講師の研修を受けられるため、研修を受けるタイミングが異なる従業員に対しても、質が同じ研修を提供できます。
いつでも・どこでも・何度でも使える
研修動画は事前に録画したデータを使用することから、動画を再生できる環境であればいつでも、どこでも、何度も視聴可能です。そのため、従業員は時間や場所を選ぶことなく研修に参加できます。なお、研修動画は何度でも視聴できるので記憶の定着が期待できるでしょう。
また、動画は配信や配布が容易であるというメリットもあります。猛威をふるっているコロナ対策としても有効で、政府が推奨しているテレワークの一環として業務に取り入れることも可能です。
動画で研修を「受ける側」のメリット
研修動画は企業側だけではなく、受ける側にもいくつかのメリットを得られます。ここからは動画で研修を受講する側のメリットを見ていきましょう。
自分の時間や都合に合わせて研修を受講できる
時間や場所が決められている集合研修では、自分の時間や都合に合わせて受講することが困難なケースも考えられるでしょう。しかし、動画を活用すれば場所や時間が限定化されないため、自分の時間や都合に合わせられます。また、日々の業務との兼ね合いを調整しやすく、従業員は隙間時間を活用して研修を受講可能です。
何度も見て復習がしやすい
研修を行う際に、事前に録画された動画を活用すれば「見逃してしまった」「聞き逃してしまった」場合でも、自由に巻き戻して繰り返し視聴できます。そのため、研修動画を受講する側は復習しやすく知識が身に付きやすいでしょう。また、復習をする際に一部の内容のみを再度視聴できるので、無駄を省いて効率的に学習を進められます。
心理的・身体的に負担が少ない
集合研修で受講する際に「発表を強いられたらどうしよう」「会場まで行くのが大変」など不安に感じる人も多いでしょう。しかし、研修動画ではこのような対面研修の心理的負担や、指定された場所へ移動する際の身体的負担がありません。そのため、比較的リラックスをして研修に取り組むことができます。
研修動画を活用するデメリット
研修動画を制作すると便利ですが、活用する際にはいくつかのデメリットも考慮する必要があります。ここでは以下の観点から研修動画を活用するデメリットを解説します。
- 動画制作のコストの負担がある
- セキュリティ対策が求められる
- コミュニケーションの機会が減る
動画制作のコストの負担がある
研修動画の制作には、コストがかかります。研修の目的や内容に応じたシーンの撮影、映像および音声の編集を行い、動画を完成させる必要があります。社内のリソースを使って撮影や編集を行う場合、本来の業務以外の負担が増えるため、従業員の負担が大きくなります。また、撮影機材の調達にもコストがかかります。動画制作会社に委託する場合には、委託費用が発生します。
そのため、ある程度のコストをかけることで得られるメリットを考慮し、効果的な動画を制作するための決断が求められます。
セキュリティ対策が求められる
研修動画では社内の機密情報を含む場合があるため、セキュリティ対策が必要です。特定のIPアドレスしか接続できないようにしたり、社内システムにログインした人だけが視聴できるようにしたりする対策をしましょう。動画配信サービスの限定公開機能や、一般的な無料のクラウドサービスを利用していると情報漏えいのリスクがあります。ID・パスワードの漏えいリスクも考慮して、情報の機密性を確保できるように対策することが大切です。
コミュニケーションの機会が減る
研修を動画で行う場合、従業員間のコミュニケーションが減少するというデメリットがあります。eラーニングとして研修動画を配信すると、研修を通じた従業員の交流の機会が減少してしまいます。研修を通じてコミュニケーションの機会を提供することは重要です。研修動画の配信後には、チャットや電話会議を通じてディスカッションの場を設けることで、この問題を解決できます。また、双方向のコミュニケーションが可能な動画配信システムを利用することも効果的です。
研修動画の種類・形式

一口に研修動画といっても講座形式やドラマ仕立てなど、さまざまな形式や種類があります。ここでは研修動画でよく使用される動画形式を3つに分類し、それぞれのメリットを紹介します。
セミナー・講座
従来のセミナー型や講座形式の研修をそのまま動画化したものが、セミナー・講座型の動画です。この形式の動画は、マナー講座や業界に必要な知識の解説講座、企業理念の解説講座、社長講話などに用いられます。講師が生徒に向かって説明している動画にすることも、実際のセミナーの様子を撮影し、動画にすることも可能です。
セミナー・講座型の動画のメリットは、制作が比較的容易なことや、テーマごとに動画を小分けできることが挙げられます。
マニュアル
マニュアル形式の動画は、業務の手順や現場の様子、接客のシチュエーションの解説などに用いられます。テキストや画像だけでは伝わりにくい動作や、複雑な手順を動画で説明できるため、視聴者が内容を理解しやすいという特徴があります。現場の雰囲気や実際の動作がわかるので、文字や画像では伝わりにくい接客業や飲食業などで多く活用されています。
マニュアル形式の動画のメリットは、実際の動作を視覚や聴覚で確認できるため、視聴者が理解しやすく、記憶に定着しやすいことが挙げられるでしょう。
ドラマ・ドキュメンタリー
ドラマ・ドキュメンタリー形式の動画は、ストーリー形式で解説を行うものです。社員が実際に働いている様子や、過去の出来事などを再現できます。ストーリー性を持たせることで、視聴者にわかりやすく伝えられるでしょう。ドラマ・ドキュメンタリー形式の動画は、会社の歴史や企業理念などの解説のほか、注意喚起やインシデントの再現などの動画で多く使用されています。
ドラマ・ドキュメンタリーは、動画の構成がストーリー仕立てになっていることから、視聴者の感情に直接訴えかけられるでしょう。具体的には、経営陣や先輩の従業員に親しみを持ってもらうことや、ドラマ仕立てのインシデント再現動画で危機感を持たせるといったことが期待できます。
研修の質を高める動画制作と運用のポイント

研修動画はさまざまなシーンで活用できるため、利便性が高いといえますが、制作の仕方によってはわかりにくい内容になってしまったり、うまく運用できなかったりすることがあります。ここでは、研修の質を高めるための動画制作のポイントや運用方法について解説します。
できるだけ短くまとめる
動画制作の際に気をつけたいのは、動画の尺をなるべく短くすることです。動画の再生時間が長いと、視聴者の集中力が落ちてしまいます。加えて長い動画は要点がつかみにくく、内容を理解することが難しくなります。長い動画は流し見されてしまう可能性があるため、なるべく要点を絞ったうえで動画を制作を行いましょう。
しかし、研修で伝えるべき内容が多岐にわたることも少なくありません。伝えるべき内容が多い場合は、要点やセクションごとに動画を分けて、短い動画を複数制作するとよいでしょう。要点やセクションを分けることで視聴しやすくなり、理解が深まります。
知りたい・必要な内容に沿って視聴しやすい環境づくり
研修動画の効率的な運用には、動画を視聴しやすい環境作りが不可欠です。研修の知識を必要とする場面ですぐに視聴できる環境を整えることで、効率的な社内教育が実現します。
また、動画配信システムを構築すると、さまざまな場所から知りたい情報にすぐにアクセスできるため、スムーズな情報共有が可能になります。動画のサムネイルをわかりやすくしたり、再生リストを設けたりすることで、アクセスしやすい環境を構築できるでしょう。
ただし動画を配信する場合は、研修動画の流出を防ぐためのセキュリティ対策が必要になるため、管理に注意しなければなりません。
動画の効果を把握する
研修動画は、視聴した従業員がどの程度内容を把握したかを確認することが難しく、動画を最後まで視聴してもらえない可能性があります。研修動画を効率的に運用するには、動画を視聴したことを確認し、従業員が内容を理解したかどうかを把握するようにしましょう。例えば、研修動画の視聴後にテストを行ったり、視聴したことをチェックしたりする仕組みを作るとよいでしょう。
また、視聴が任意となっている場合は視聴されない可能性があります。その場合は視聴数や視聴時間を計測して、成果を把握することが大切です。
研修動画の実際の作り方

研修の効率化を図れる研修動画ですが、どのような手順で制作すればよいのでしょうか。ここからは、研修動画を制作する手順を紹介します。
研修の全体像を描く
動画を制作する前に、ますはどのような研修を行うかを事前に決めておくようにしましょう。研修動画に限りませんが、動画は制作後の修正が難しく、完成までに時間がかかる可能性があります。そのため、外部に制作を委託する場合は研修の全体像を決めて、制作会社に明確に伝えるようにしましょう。研修で従業員に伝えたい内容を洗い出し、できるだけ細かく構成を組み立て、動画に反映する要素を明確に決めておくことが大切です。
しかし、研修によっては動画以外の方法が適している場合もあります。動画以外に、ワークショップ形式や文書の読み合わせ、OJTなど、ほかに効果的な研修がないか検討することも必要です。
それぞれの研修動画の仕様を固める
研修動画の骨子や構成が決まれば、次に動画の仕様を固めます。具体的には動画形式や長さ、スタイルといった動画自体の仕様を決めましょう。目的によって最適な動画形式が異なるだけでなく、動画形式によって最適な長さも変わるため、しっかり検討することが大切です。
また、視聴や配信、配布の方法によって効率的な研修が行えるかが決まるため、研修動画の視聴や配信、配布などの運用方法も明確にします。動画の内容によっては、セキュリティを考慮した視聴・配信・配布方法が必要になるケースもあるため、。動画の仕様とともに、運用方法の仕様も固めましょう。
実際に動画を制作する
仕様が固まれば、動画の制作に入ります。セミナーやスピーチをそのまま撮影するのであれば、自社でも研修動画の制作は可能です。しかし編集が必要な場合や、マニュアル形式など複雑な動画を制作する場合は制作会社に依頼したほうがよいでしょう。
特に企業理念や経営方針といった難しい内容を伝える動画や、ストーリー性がある動画の制作は容易ではありません。効率やコストの観点でも、制作会社に依頼することをおすすめします。
研修動画を外注する際の費用相場
研修動画を外注する際の費用相場は、動画の長さや構成、撮影形式などによって変動します。以下では、「セミナー・講座」「マニュアル」「ドラマ・ドキュメンタリー」の費用相場をそれぞれ紹介していきます。
セミナー・講座形式の研修動画
セミナー・講座形式の費用相場は、一般的に30~70万円となっています。基本的にセミナー・講座の様子を撮影するのみで、特殊な編集が必要ないため、費用を抑えられる場合が多いでしょう。ただし「セミナーや講座の長さ」「編集作業の工数」「撮影場所」などによって、費用が変動することを理解しておきましょう。
マニュアル形式の研修動画
マニュアル形式の費用相場は、40~90万円となっています。こちらも編集作業が少なく、動画の尺が短めであることが多いため、他形式と比べて費用を抑えられるでしょう。しかし、動画の品質を高めるには、ナレーションや字幕を入れる必要があります。その場合は費用が高くなる可能性があることを理解しておきましょう。
ドラマ・ドキュメンタリー形式の研修動画
ドラマ・ドキュメンタリー形式の費用相場は、80万円以上が一般的といえます。ドラマ・ドキュメンタリー形式の場合は、ストーリー構成の考案や複数の場所での撮影など、他形式と比べて制作会社の工数が多くなります。そのため、他形式と比べて費用が高くなる傾向にありますが、ストーリー性を持たせて視聴者の感情に訴求したい場合に効果的です。
研修動画の導入事例

ここまで研修動画について解説してきましたが、実際に研修動画は企業でどのように活用されているのでしょうか。ここでは実際に研修動画を導入した企業や、研修動画の事例を紹介します。
株式会社クリッククローバー様(PROOX制作動画)
全国のさまざまな店舗で販促支援や販売支援人材派遣を行っている株式会社クリッククローバー様は、新人のために基本的な業務知識を伝えるマニュアル動画を制作しました。これまではマニュアルの読み合わせや説明会などを開催していましたが、マニュアル動画を導入したことで業務の効率化や研修の共通化のほか、受講者に現場の雰囲気を伝えることができるようになっています。
また、動画にイラストを挿入することで、テキストの役割も果たせる作りになっています。
Sansan株式会社様(PROOX制作動画)
名刺管理システムをはじめとしてさまざまなビジネスサービスを展開しているSansan株式会社様は、営業ツールの一環として顧客向けのチュートリアル動画を制作しました。実際のサービスの画面を使用し、使用方法や活用方法を説明しています。
シンプルでありながらも細部までデザインにこだわり、「見やすい」「わかりやすい」を追求した動画はサービスの使用をイメージしやすく、誰でも簡単に活用できることが理解できるものになっています。
研修を効率化させるために動画を活用してはいかがでしょうか
企業の人材育成や教育に欠かせない研修は大切ですが、手間がかかるうえにコストも高額になりがちです。しかし、大きな負担となっている研修は「動画化」することで、効率化やコスト削減が期待できます。動画を活用することで、従来の研修では伝わりにくかったことがうまく伝わるケースも大いにあるでしょう。
現在はコロナの影響で従来の研修が難しく、政府はテレワークを推進しています。感染拡大の防止だけでなく、業務改革やコスト削減、研修の効率化を図るためにも、研修動画の導入を検討してはいかがでしょうか。
研修動画に関してよくあるQ&A
最後に、研修動画に関してよくある質問をQ&A形式で3つ紹介します。研修動画に関して疑問に感じた際は、下記の内容を参考にしてみてください。
Q. 研修に動画を活用するメリットは?
A. 企業側にも受講者側にもさまざまなメリットがありますが、主に以下のようなことが挙げられます。
- 研修のコストを軽減できる
- 内容をより正確に理解してもらえる
- 何度でも研修で使用できる
- 時間や場所を気にせず受講できる
- 受講者の心理的・身体的に負担が少ない
Q. 研修動画の種類や形式は何がありますか?
A. 研修動画の形式は主に「セミナー・講座」「マニュアル」「ドラマ・ドキュメンタリー」の3種類です。
なお、撮影形式によって費用相場が異なります。
Q. 研修動画の品質を高めるための制作や運用のポイントは?
A. 研修動画の品質を高めるためのポイントは主に以下の3つです。
- 研修動画をできるだけ短くまとめる
- 知りたい・必要な内容に沿って視聴しやすい環境を構築できる
- 研修動画の効果を把握する