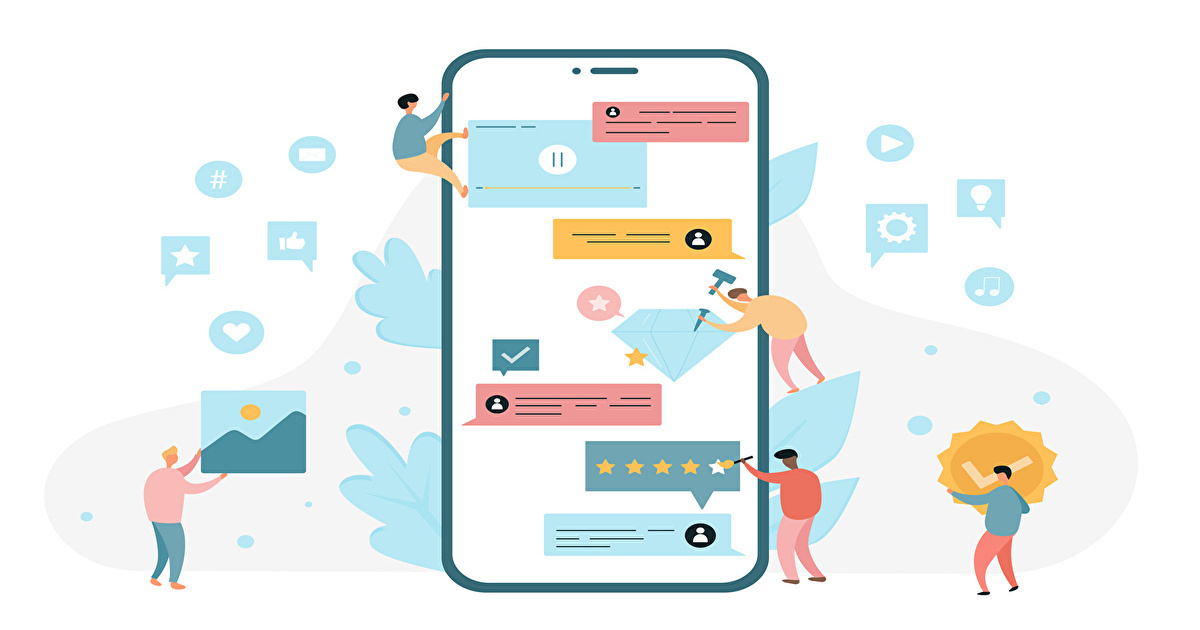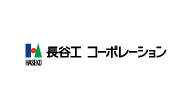動画を、広報や宣伝に使うだけでなく、ライブ配信に活用する企業が増えています。ライブ配信はリアルタイム性やコミュニケーション性に優れているため、新商品の発表会や株主総会、公開セミナーなどでの活用が注目されています。
ライブ配信は通常の動画制作とは異なるノウハウが必要であり、計画や準備を入念に行うことが大切です。
本記事では、企業におけるライブ配信の活用方法や、準備すべきものなどについて解説します。
また、プルークスでは、動画制作・映像制作、縦型ショートドラマ、ショート動画運用など、様々なコンテンツに役立つ限定ダウンロード資料をご用意しています。実践に活かせる事例とノウハウが詰まったコンテンツをぜひご活用ください。
目次
ライブ配信とは?
まず、ライブ配信の定義や、一般的な動画配信にはないライブ配信ならではの特徴について解説します。
ライブ配信とは
ライブ配信とはリアルタイムで動画を配信することで、通常の動画配信方法であるオンデマンド配信(※1)とは区別されます。テレビの生放送にあたるため、「生配信」と呼ばれることもあります。
(※1)視聴者が好きなときにいつでも視聴できる動画
ライブ配信の特徴について
ライブ配信の大きな特徴の一つが「双方向性」です。ライブ配信中に視聴者からのコメントに反応したり、クイズや投票など視聴者が参加できる企画を入れたりすることが可能です。
オンデマンド配信と比べると、視聴者のアクションに対して素早く反応でき、リアルでのやり取りに近いため、視聴者との距離が近くなり、お互いの感情がダイレクトに伝わります。
ライブ配信とオンデマンド配信の違い
オンデマンド配信の動画であれば、配信者がカットなどの編集を行ったうえでアップロードできます。しかし、ライブ配信動画の場合は後から編集ができません。そのため、配信中のトラブルを想定した入念な準備が求められます。
配信する際は、背景や周囲の雑音、明るさ(照明)などを配慮しましょう。機材やネットワークのトラブルでライブ配信が中断することがないように、事前に準備する必要があります。
また、ライブ配信動画は編集が不要であるため、編集にかかるコストを削減可能です。
ライブ配信の活用事例


企業のライブ配信は、どのような場面で活用されているのでしょうか。ここでは、主な活用事例を紹介します。
自社イベント中継
記者会見や展示会、新商品の発表会などの自社イベントの生中継は、企業のライブ配信で多く見られるコンテンツです。企業によっては、スポーツの試合やコンサートの様子などを配信し、事前に入場トークンを販売したり、投げ銭機能を使ったりして収益化するケースもあります。
セミナー、株主総会
Web上で行うセミナーは生配信であれば、その場でコメントへの応答や多数決などの投票もできます。場所や移動コストがないため集客が容易であり、予約・設営にかかるコストを抑えられるでしょう。
採用説明会
ライブ配信による採用説明会は、オンライン面接と併せて企業と求職者の双方の負担を減らせる新しい採用のあり方として注目されています。ライブ配信による採用説明会は、企業側と求職者側が画面を通してコミュニケーションを取りながら進めるケースが多いです。
社内の朝礼、交流会、勉強会など
ライブ配信は社外向けのものだけでなく、朝礼や交流会、勉強会などの社内活動にも活用できます。場所を問わず参加できるため、従業員の負担を減らし、複数の拠点を持つ企業でも意思統一がしやすいでしょう。一つの場所でイベントを実施できるため、運営部署の負担も軽減できます。
ライブ配信のメリット・デメリット


ここからは、ライブ配信のメリットとデメリットについて解説します。デメリットを最小限に抑え、メリットが最大化できるようなライブ配信を目指しましょう。
ライブ配信のメリット
ライブ配信の主なメリットは、以下の通りです。
・場所の予約や準備の手間が省ける
セミナーなどのオフラインイベントでは、会場の予約や設営などの準備が必要です。会場に空きがないと、日程変更や複数回開催などの必要があり、スケジュール変更を余儀なくされるケースもあります。ライブ配信であれば、撮影場所の予約や準備だけで済み、参加者数に合わせて会場を準備する必要もないため、計画を立てやすいでしょう。
・参加率が向上する
ライブ配信イベントの場合、参加者はパソコンやスマートフォンなどを通して都合のよい場所から参加できるため、参加率が向上します。場所の制約がないため世界中から参加でき、コロナウイルス感染などの心配もありません。
・編集の手間が省ける
ライブ配信はオンデマンド配信と比べると企画の手間はかかりますが、動画の編集は不要です。ライブ配信後にオンデマンドでも動画を配信する場合でも、ライブの雰囲気を残すために最小限の編集で済ませるケースがほとんどなので、制作サイドの負担が軽くなります。
・投げ銭機能によるマネタイズができる場合がある
YouTubeなどのライブ配信プラットフォームには、投げ銭機能を持つものもあります。投げ銭機能とは、動画配信者を支援するために視聴者が寄付できる機能です。
有益な情報を提供するコンテンツやエンタメ性の高いコンテンツでは、視聴者がライブ配信中に投げ銭を行うことがあります。ライブ配信中に投げ銭をしたユーザーのコメントには必ず反応するなど、リアクションの方針を決めておくとよいでしょう。
ライブ配信のデメリット
一方で、ライブ配信には以下のデメリットがあるため注意が必要です。
・ライブ配信に関するノウハウが必要
ライブ配信動画は編集ができないため、出演者のトークスキルやコメントへの対応力が求められます。効果音やテロップなどの演出はオペレーターが行いますが、タイミングやスピード次第では、配信の質を落としかねません。
また、コメント対応や生アンケートといった演出でライブ感を高めることや、ネットワークや周辺環境から生じるトラブルへの対応力なども問われます。
実際にいろんなライブ配信に参加して、参考にするのもよいでしょう。さまざまな工夫や対応方法を知ることができるのでおすすめです。
・ライブ配信用の機材、サービスが必要な場合がある
ライブ配信では、動画データを配信用のデータに変換(エンコード)するソフトが必要です。この処理は負荷が大きいため、安定的に配信するためにはデバイスにも高い性能が求められます。エンコード用ソフトは無料のものも多いですが、外付けのライブエンコーダーは数万円から数十万円とやや高価です。
また、配信用プラットフォームを使う場合、グループを分割する機能や株主総会用の議決権機能は有料オプションであることが多く、追加コストが発生します。
配信中には、回線トラブルにより遅延が起こる可能性があります。そういったトラブルの対処法として、高速で安定したインターネット回線が必要であり、それにもコストがかかります。
・リアルのイベントと比較して臨場感や一体感に欠ける場合がある
ライブ配信のメリットは双方向性や臨場感ですが、それはあくまでもオンデマンド配信と比べた場合であり、リアルタイムのイベントには遠く及びません。例えば、視聴者はカメラの映像しか見ることができないため、他の視聴者(イベント参加者)の反応はわからず、他の観客と一緒に盛り上がるといった体験は難しいです。
また、コメントへの対応が遅い、通信状態が悪いといった場合はしらけてしまい、視聴離脱が多発することもあります。
ライブ配信のやり方・方法
ここからは、ライブ配信を行う際の流れを見ていきましょう。適切な流れを理解したうえで、ライブ配信を行うことが大切です。
ライブ配信のやり方①:企画
通常の動画制作と同様に、ターゲットを明確にして有益なコンテンツを企画します。配信時の演出や、配信後にアーカイブを公開するどうかも事前に決めておきましょう。また、成果指標がないとライブ配信の効果を検証できないため、成果指標も企画段階で明確にしておくことが大切です。
ライブ配信のやり方②:告知・案内
マーケティング部門や広報部門などと協力して、ターゲットへの告知・案内を行います。また、撮影場所に応じて周囲に必要な協力を要請します(できるだけ静かにする、カメラに写りこまないよう注意するなど)。
ライブ配信のやり方③:リハーサル
生放送を行う前に、必ずリハーサルを行いましょう。実際にカメラを回してテスト配信を行い、スタッフが視聴して音量や見え方などをチェックします。リハーサルで気になることは、確実に本番前に解決しましょう。
ライブ配信のやり方④:配信
視聴者の反応を確認しながら、ライブ配信を進行します。トラブルで開始が遅れたり、予想以上に盛り上がって予定の時間を過ぎたりすることもありますが、そのような場合はディレクターを中心に、柔軟に対応しましょう。
ライブ配信アプリを選ぶ際に確認すべきポイント


昨今では、スマートフォンでライブ配信を行えるアプリが数多く存在します。手軽に利用できるライブ配信アプリは魅力的といえますが、どれを選ぶべきか迷う人も多いのではないでしょうか。
ここでは、ライブ配信アプリ選びで確認すべき3つのポイントについて解説します。
ユーザー数の多さ
ライブ配信アプリのユーザー数は、初めに確認すべき項目です。自身の配信は、ライブ配信アプリのユーザーが視聴してくれます。ユーザー数の多いアプリを選べば、多くの人に配信を視聴してもらえる可能性は高まるでしょう。
アプリによっては、ユーザー数を公表していない場合もあります。しかし、ユーザー数が多いアプリであれば、セールスポイントであるユーザー数を公表していることが多いでしょう。ユーザー数だけでアプリの優劣は決まりませんが、検討する際の一つの指標として考慮することをおすすめします。
配信するジャンルと利用者のニーズが適合するか
配信するジャンルと、利用者のニーズが適合するか確認することも大切なポイントです。多くのライブ配信アプリには、「ゲーム配信」や「雑談配信」といった配信ジャンルを設定する機能があります。ユーザーは興味のあるジャンルでライブ配信を探すことも多いため、配信ジャンルと利用者のニーズが適合しているか確認するようにしましょう。
ライブ配信アプリによってユーザーの傾向が異なるため、配信ジャンルごとの需要も変わってきます。例えば、若年層のユーザーが多い場合、ビジネス系の配信は視聴されにくいでしょう。そのため、自身が配信するジャンルに関心のあるユーザーが多いアプリを選ぶほうが、視聴される可能性が高まります。
通信回線の速度
ライブ配信アプリの通信回線速度が問題ないかも確認しましょう。双方向のコミュニケーションをともなうライブ配信には、高いリアルタイム性が求められます。通信回線の速度が遅いアプリだと、ライブ配信中に動作が重くなり、視聴者が離脱してしまう可能性があるでしょう。
ライブ配信の魅力であるリアルタイム性を失わないためにも、通信回線の速度が考慮が欠かせないポイントです。
ライブ配信で必要になもの


ライブ配信を行うにあたって必要となるものについて、簡単に紹介します。ライブ配信アプリを用いるかどうかで、必要なものは下記のように変わります。
| 1.いずれかを選択 | A:ライブ配信アプリ |
| B:ライブ配信用の機材・設備 | |
| 2.ライブ配信に必要な人材・役割 | |
必要なものが欠けてしまうと、質のよい配信は実現できないため、事前に準備しておくようにしましょう。それぞれについて、順番に説明します。
ライブ配信に必要なものA:ライブ配信アプリ
ライブ配信アプリを用いる場合、ライブ配信用の機材・設備を用意せずに始められるでしょう。ライブ配信用アプリには、有料のものと無料のものがあります。プラットフォームによって機能や対応人数が異なるため、自社の規模や目的に合うものを選びましょう。
YouTube Live
「YouTube Live」は、動画共有サービス「YouTube」のアプリでライブ配信が行える機能です。YouTubeは世界中のユーザーが利用する人気サービスであり、特定の配信ジャンルを問わず多くのユーザーをターゲットにできる魅力があります。
YouTube Liveは誰でも無料で利用でき、コメントによる視聴者とのやり取りだけでなく、アンケート機能なども利用可能です。また、ユーザーからの投げ銭を「スーパーチャット(報酬)」として受け取れるため、マネタイズも容易にできます。
配信後はアーカイブとして動画を残せるのも魅力といえるでしょう。配信アプリの選択に迷った場合はYouTube Liveを選ぶことをおすすめします。
Zoom
「Zoom」はビジネス向けのビデオ会議ツールとして広く認知されていますがライブ配信機能を持つアプリ版もあります。チャット機能や「手を挙げる」機能により、配信者・ユーザー間のコミュニケーションも可能です。仕事でZoomを用いている人であれば、操作に迷うことも少ないため、Zoomの利用をおすすめします。
TwitCasting Live(ツイキャス)
「TwitCasting Live(ツイキャス)」は、アクティブユーザー数が多い人気のライブ配信アプリです。特徴として、通信速度制限がかかった状況でもライブを比較的快適に視聴できるモードがあります。また、コミュニケーションを行うための基本機能も備わっているため、操作に迷うことなく容易に利用できるでしょう。
SHOWROOM
ストリーミングサービスとして知られる「SHOWROOM」は、スマートフォンでのライブ配信も可能です。仮想的なライブ空間に視聴者がアバターとして参加するという、独特な配信スタイルとなっています。カラオケやダンス、コスプレなどの配信ジャンルがあり、女性人気が高い配信アプリです。
インスタライブ
「インスタライブ」は、人気SNS「Instagram」に搭載されているライブ配信機能です。最長4時間ものライブ配信が可能で、配信終了後の動画は「ストーリーズ」という部分に自動保存されます。ただし、ストーリーズの配信自体は24時間限定であることをあらかじめ理解しておきましょう。
ニコニコ生放送
「ニコニコ生放送」は、人気動画共有サービス「ニコニコ動画」の運営元が提供するライブ配信アプリです。動画配信として歴史が長いこともあり、24時間監視といった荒らし対策が充実しています。安心してライブ配信したい人におすすめの配信アプリといえるでしょう。
Vimeo
アメリカの企業が運営している動画共有サービス「Vimeo」には、ライブ配信が行えるアプリ版もあります。ライブ配信には有料の会員登録が必要ですが、高画質なライブ配信が行えることが魅力です。海外のユーザーが多いため、外国人もターゲットとしたい人は利用してみるとよいでしょう。
ULIZA
「ULIZA」は、国内向けの動画配信プラットフォームです。アプリ版は存在しませんが、クラウドサービスのためスマートフォンでも利用できます。プロ向けの高品質なライブ配信が可能であり、ビジネス向けの利用者が多いことが特徴です。
ライブ配信に必要なものB:ライブ配信用の機材・設備
ライブ配信アプリを使わない場合は、専用の機材・設備を用意しましょう。オンデマンド配信の場合と大きくは変わりませんが、配信用のデバイスやインターネット回線には高い性能が求められます。
・ライブソース
配信する動画コンテンツ
・撮影機材
ビデオカメラ、三脚、マイク、照明、ケーブル類など
・配信用サーバーor配信用プラットフォーム
自社でサーバーを準備する場合、ネットワークの帯域圧迫やセキュリティ、他業務への影響に注意が必要です。
・インターネット回線
無線よりも有線のほうが安定します。配信を安定させるためにも高性能なものがベターで、できれば配信用の回線は別途準備することをおすすめします。
・ライブエンコーダー
カメラで撮影した映像をパソコンに取り込み、配信可能な形式に変換するためのソフトです。有料のもの、無料のものがあります。
・視聴用のWebページ
必要に応じて、動画視聴用のWebページを用意します(配信用プラットフォームを使う場合は不要)。
ライブ配信に必要な人材・役割
ライブ配信の規模によっては、特別な役割を持つ人材が必要です。ライブ配信に必要なスタッフとその役割を簡単に紹介します。
・ディレクター
配信するコンテンツの企画・構成や環境整備、各種調整を行う責任者です。
・MC
配信する番組の進行役で、セミナーなどでは司会者が兼ねるケースもあります。
・カメラマン
配信する番組の撮影を担当する人で、人数はコンテンツの規模や演出によって変わります。
・ビデオエンジニア
デジタル機材の設営や配信を担当するIT技術者で、当日はオペレーターとなることもあります。
・オペレーター
配信時のBGMやSEの再生、テロップ作成、画面の切り替えなどを担当します。
ライブ配信を活用して上手に情報を発信しよう
通常のオンデマンド配信にはない特徴を持つライブ配信は、企業における新しい情報発信の方法として注目されています。
ライブ配信にあたってはコンテンツ設計が非常に重要になるので、ライブ配信のメリットが活きるように企画しましょう。機材の準備や運用には多少のコストと慣れが必要であり、一から揃えるとなると、費用と時間が発生します。そのため、動画制作のプロに相談することは、ライブ配信を上手に活用するための手段だといえます。
ぜひライブ配信を活用し、自社のマーケティングやブランディングに活用してください。
ライブ配信に関してよくあるQ&A
ここからは、ライブ配信に関してよくある質問をQ&A形式で紹介します。
Q. ライブ配信を行うメリットは何ですか?
A. ライブ配信を行うメリットは、以下の通りです。
- 場所の予約や準備の手間が省ける
- 参加率が向上する
- 編集の手間が省ける
Q. ライブ配信で必要なものは何ですか?
A. 主に以下のようなものが必要です。
- 動画配信用プラットフォーム
- ライブ配信用の機材・設備
- 必要な人材・役割の手配
Q. ライブ配信はどういったシーンで活用できますか?
A. 主に以下のようなシーンで活用できます。
- 自社イベント中継
- セミナー、株主総会
- 採用説明会
- 社内の朝礼、交流会、勉強会 など
ライブ配信に関するnoteも公開中です!ぜひ御覧ください。
【インタビュー】1対nコミュニケーションの代替手段「ライブ配信」プロジェクトをまとめた時の話。