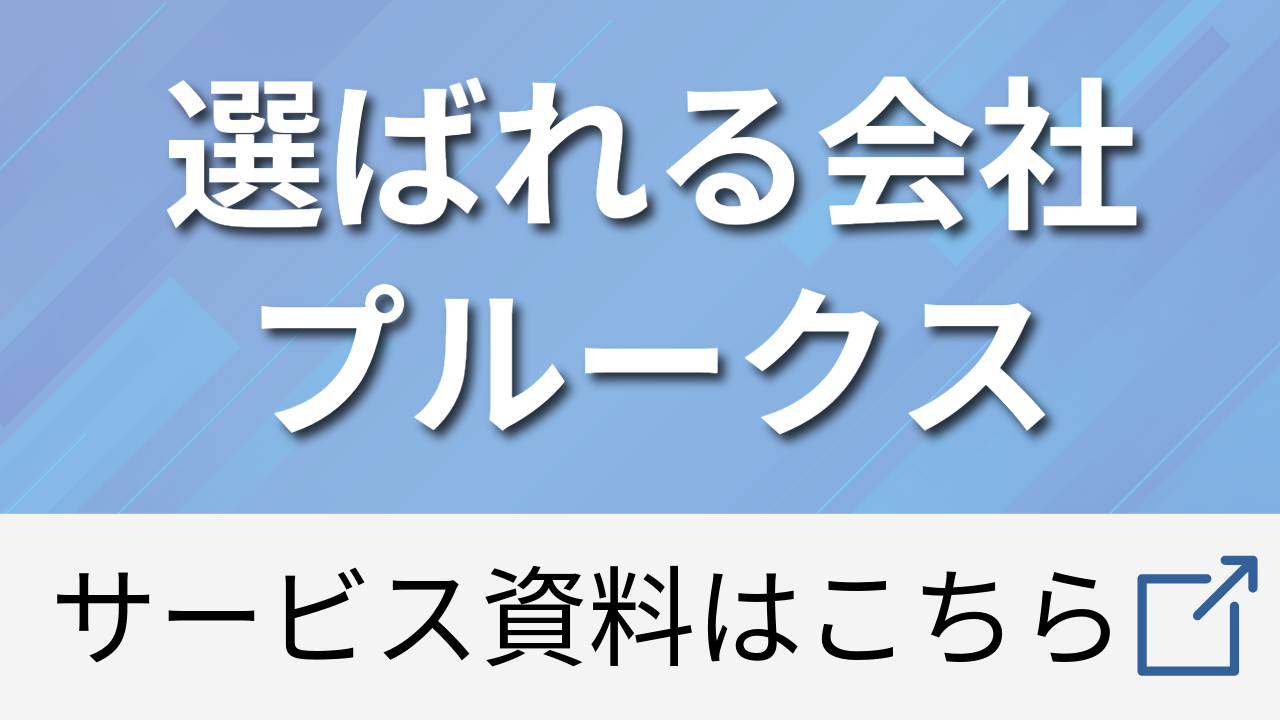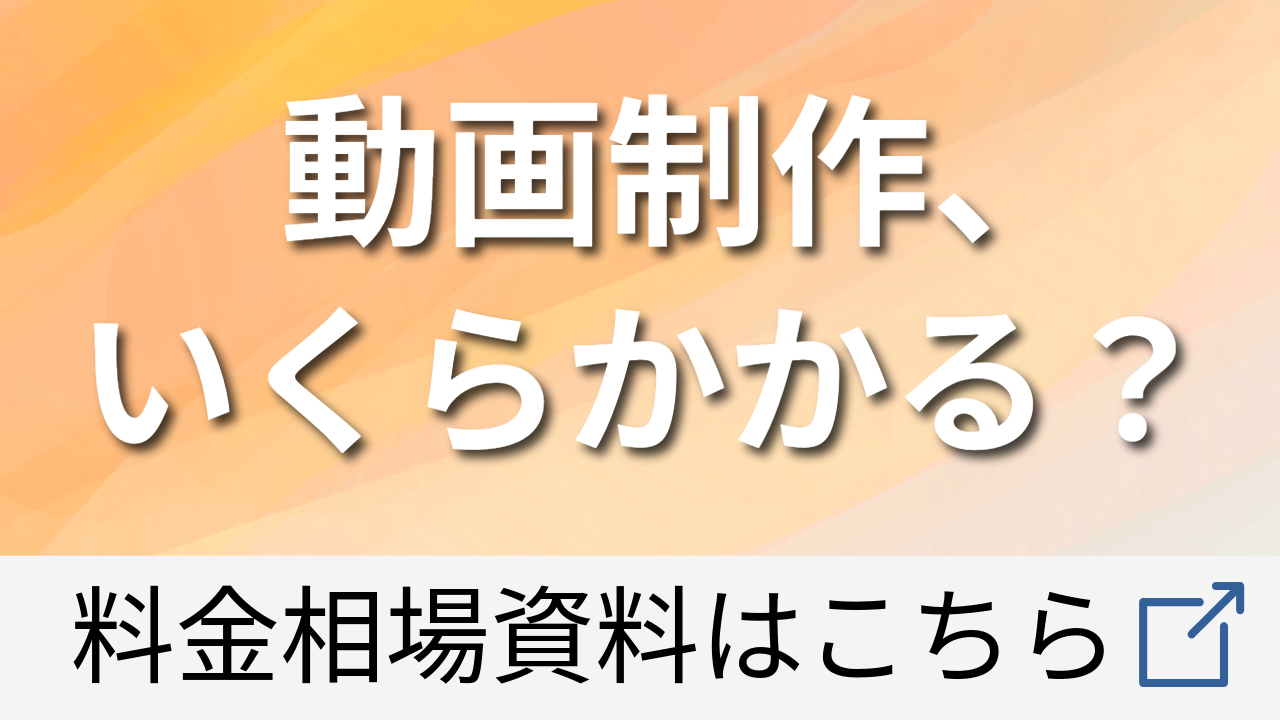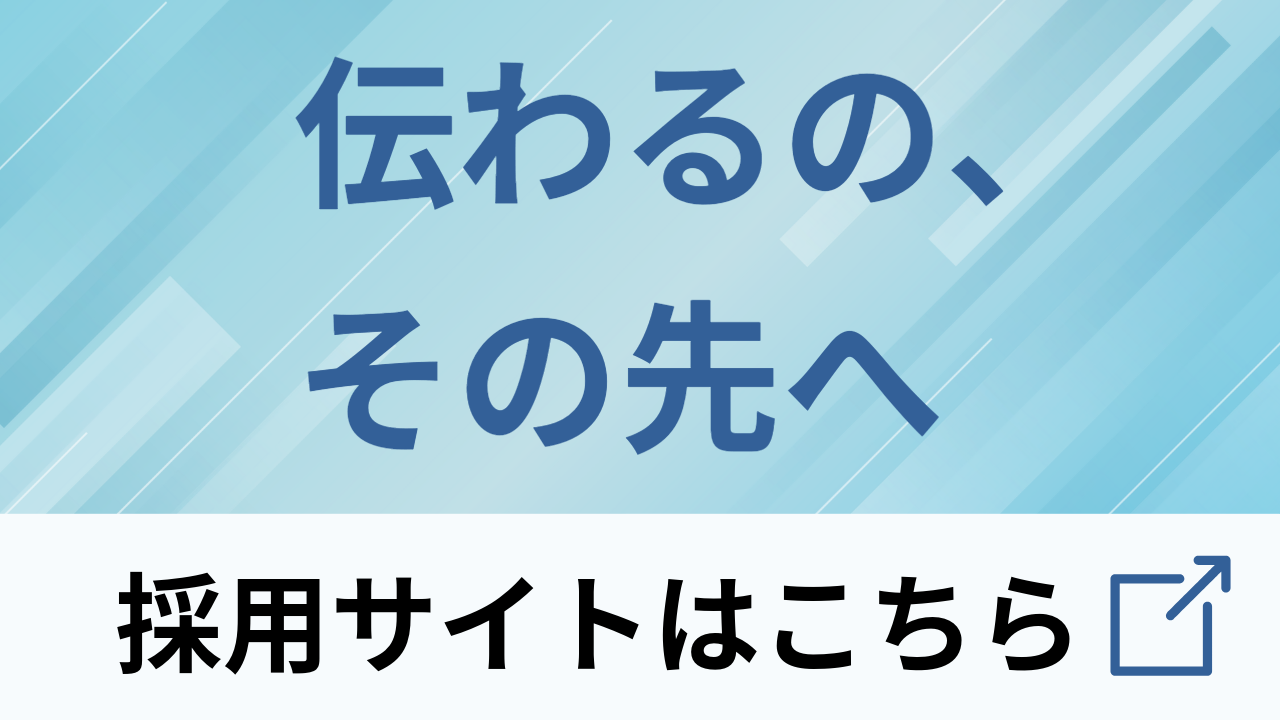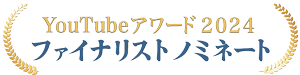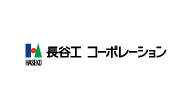ブランディング動画とは、映像を通して、自社のブランドや製品、サービスを消費者に認知してもらう目的で作られるものです。昨今では、テレビCMやYouTubeなどでさまざまな企業のブランディング動画が見られるようになり、動画を利用してブランディング向上を図る企業が増えてきています。
今回は、ブランディング動画の基本的な内容やメリット、動画制作のポイント、動画の活用事例について詳しく解説します。
また、プルークスでは、動画制作・映像制作、縦型ショートドラマ、ショート動画運用など、様々なコンテンツに役立つ限定ダウンロード資料をご用意しています。実践に活かせる事例とノウハウが詰まったコンテンツをぜひご活用ください。
目次
ブランディング動画(ブランディングムービー)とは?


ブランディング動画とは、企業そのものや企業が販売する商品・サービスの認知、イメージアップのための動画を指します。ここでは、そもそもブランディングの定義とは何か、またブランディング動画を制作する目的について詳しく解説します。
ブランディングの定義とは
ブランディングとは、ブランドを形成するための活動のことです。売り込むことが目的ではなく、消費者がそのブランドを認知し購買意欲を掻き立てることを主な目的としています。
ブランディングの最終的な役割は、ブランドイメージを定着させることです。したがってブランディング動画は、企業の理念・信念、ビジョンを視覚的に伝え、認知を広げるための動画といえます。
では、「ブランド」とは何でしょうか。ブランドは、高級品を指す言葉ではありません。消費者によって商品・サービスが「識別されている」場合、それらはブランドと呼ばれます。消費者に識別・認知されることで、はじめて「ブランドが定着した」といえます。
ブランディング動画と動画広告の違い
ブランディング動画は、企業やブランドの価値観、理念、世界観を視聴者に伝えることを目的としています。視覚的に魅力的で感情に訴えるストーリーテリングを用い、長期的なブランドの認知度向上や信頼感の醸成を目指します。具体的な商品やサービスの訴求よりも、ブランド全体の印象を強化することが重視されます。
一方動画広告は、特定の商品やサービスを直接的に宣伝し、購入や問い合わせといった即効的な行動を促すことを目的としています。短期間で効果を得るために、具体的で明確なメッセージや強いコール・トゥ・アクションが特徴です。視聴者の興味を引き、直接的な効果を追求する内容が中心となります。
ブランディング動画制作の目的
そもそもブランディング動画を制作する目的とは何でしょうか。ブランディング動画を制作する目的を理解しなければ、その効果は期待できません。動画を制作する目的は、「認知度を高めること」「共感を得ること」「差別化を行い、消費者に選択してもらうこと」です。
ブランディングを行うことで認知度は上がりますが、単に認知度を上げること自体が主な目的ではありません。商品・サービスに価値を感じている消費者など、ターゲットを意識してブランディングを行い、ターゲットに対する認知度を上げることが大切です。
ブランディング動画を制作をすることは、自社の商品・サービスに一層魅力を感じてもらい、信頼関係を構築するための架け橋といえます。
ブランディング動画に注目するべき理由
スマホが普及し、場所と時間を問わず自由に映像を見られるようになったことで、動画の需要は高まっています。またYouTubeやInstagramなどSNSの利用機会が増えて、以前と比べ動画を見る機会が増えていることも挙げられます。
以下では、ブランディング動画を制作するメリットについて解説します。
ブランディング動画を制作するメリット


ブランディング動画)の制作にはどのようなメリットがあるのでしょうか。最大のメリットは、伝えたい情報を視覚的に、的確に伝えられることです。視覚的に伝えることでどのようなメリットがあるのか、一つずつ確認していきましょう。
感覚や感情に訴えやすい
ストーリー形式で制作されたブランディング動画は、視覚と聴覚に訴えることができるため、消費者の感情を刺激し、共感を引き出すことができる手法です。静止画で商品・サービスの魅力を伝えることもできますが、動画のほうがより効果的に伝えることができます。動画は画像の集合体です。例えば「60fps」の場合、1秒間に60枚の画像を連続で見ていることになります。その情報量は、画像の比ではありません。
感情を数値化することはできませんが、1秒間に60枚の画像情報を受け取ると考えれば、60倍の情報を得られる分、感情が大きく揺さぶられることがイメージできると思います。
SNSでの自発的拡散を狙える
SNSによって動画に対する共感が広がっていくことも、ブランディング動画を制作する一つのメリットです。制作した動画がSNSでリツイートされたり、インフルエンサーによって取り上げられたりすることで、ブランドの情報は加速度的に拡散します。Instagram・YouTubeなど若い世代が利用しているSNSアプリでの拡散は、ブランディングの効果をより高めてくれます。
動画を多くの人に見てもらうためには、動画広告を出すなど広告費用が掛かるケースもありますが、SNSで自然と拡散されれば、広告費を圧縮できるというメリットもあります。
SNSに関して以下の記事で紹介しておりますので、気になる方はぜひご一読ください。
動画配信に適した6大SNSとは? 最適な長さと成果につながる制作方法
BtoBでも効果が期待できる
動画マーケティングのターゲットには、対消費者向けの「BtoC」と対企業向けの「BtoB」があります。一般消費者向けの商品やサービスは、日常的に触れる機会が多いため、CMなどを通して、数多くのブランディング動画が展開されてきました。
ただし、ブランディング動画によってブランド力が高まるのは、BtoCだけではありません。これまで可視化されていなかった商品・サービスの魅力が、動画によってより効果的に伝わるため、BtoBにおいてもブランディング効果が期待できます。
ブランディング動画制作をすることで、文字で構成されたWebページよりも効果的に伝わるようになり、難しい内容もわかりやすく説明できます。BtoBのターゲットを絞り込んで制作すれば、低コストで成約に結びつけることもできるでしょう。
ブランディング動画制作で想定される効果
ここからは、ブランディング動画がもたらす具体的な効果を4つ紹介します。一つずつ見ていきましょう。
ブランド認知度の向上
ブランドの認知をあげることは、企業にとって非常に大切なことです。動画は文字や画像だけでは伝えきれないブランドのストーリーや雰囲気をより効果的に伝えることができます。
見た人の共感を集められる内容のブランディング動画を制作することで、SNSなどで拡散されやすくなるため、ブランドの認知度向上につながります。その結果、ターゲット層だけではなく、たくさんの人にブランドを知ってもらうことができます。
また、動画を見て商品やサービスに興味を持った人が、次のアクションとして、その企業について検索したり、実際に商品やサービスを利用したりするなど、具体的な行動を起こすきっかけにもなります。
企業の信頼性・権威性の向上
ブランディング動画を通じて視聴者の感情を動かし、共感を得ることができれば、ブランドだけではなく、企業の信頼度も高めることができます。
例えば、消費者からは普段知ることができない商品の製造工程や衛生管理を映すことで、「この企業はしっかり品質管理できているな」という信頼性を感じてもらえます。また、経営者やスタッフの言葉をブランディング動画を通じて発信することで、「この企業は他とは違う」という権威性を与えてくれます。これにより、企業が持つ影響力が増し、他の企業との競争において優位に立つことができるようになります。
企業の評価が高まり、市場での企業価値が向上することで、株価が上昇するなど持続的な成功が期待できるようになるでしょう。
顧客とのエンゲージメント強化
ブランディング動画を作ることで、顧客とのエンゲージメントは高まります。TVCMも同様ですが、効果的なビジュアルや音楽で顧客に訴えかけることは、顧客がブランドに対して親近感を感じやすくなります。
製品の作り手のこだわりやストーリーを伝えることで、顧客は「この企業は自分の価値観と合っている」と感じ、より応援したいという気持ちが芽生えます。これが、エンゲージメントを高める一つの方法です。
さらに、YouTubeやSNSのコメントを通じて顧客の意見を取り入れることで、双方向のコミュニケーションが活性化し、エンゲージメントのさらなる強化が期待できます。このように、ブランディング動画を通じて、顧客とのつながりや関心を深めることで、より強いエンゲージメントが生まれるのです。
長期的なブランド価値の向上
ブランディング動画には、長期的にブランド価値を維持・向上させる効果があります。
一般的な商品やサービスの広告動画は、販売促進が主な目的のため、効果は短期的なものになりがちです。一方で、企業や商品のブランディングを目的としたブランディング動画は共感や感動を通じてブランドイメージを強化することを目的としているため、継続的かつ長期的な効果が期待できます。
また、一度ブランドや製品のファンになった顧客は、新しい商品やサービスが登場した際に購入しやすくなるだけでなく、SNSなどで自主的に情報を拡散するなど、前向きなユーザー行動につながる可能性があります。
ブランディング動画制作のポイント


ブランディング動画を制作する際に気をつけるべきことは、「伝わる」ポイントを理解することです。そこで、コンセプトや共感性、ストーリーなど、ブランディング動画制作において重要なポイントを解説します。
一貫したコンセプトを確立する
情報を動画で伝える際、内容にばらつきがあれば、何を伝えたい動画なのか不明確なため、視聴者に思うように伝わりません。コンセプトに一貫性がない動画では、視聴者に的確にブランドイメージを伝えることはできないのです。
例えば、伝えるべきことが自社の強みや他社より優れている点であるとしたら、それを伝えるために動画に一貫性を持たせる必要があります。ブランディング動画制作にあたっては、自社の強みは何なのか、社内で議論を行い、コンセプトを確立して制作に臨みましょう。
また動画の背景や音楽、フォントにもコンセプトに沿った一貫性が求められます。
それらをすべて洗い出してから動画制作を行うことではじめて、一貫性のある明確な情報を伝えることができます。
共感が得られる内容にする
当然ながら、動画で情報を発信するだけでは不十分です。情報を受け取る視聴者が「共感」しなければ、そのブランディング動画には意味がありません。
共感を得るために必要なのは、独自の世界観です。商品を紹介する動画に対してBGMを使用せず、淡々と商品を説明するだけでは共感を得られないでしょう。視聴者は、その映像や音楽を通じて情報を受け取り、共感することではじめて行動を起こします。
押し付けられた情報を受け取れば、視聴者は興味を失ってしまいます。独自の世界観のあるブランディング動画によって共感を得て、行動を起こしてもらえるような動画を制作する必要があるといえます。
ストーリー性を持たせる
ブランディング動画を制作する際には、視聴者の興味・関心をそそるような動画制作が求められます。コンセプトを確立し、視聴者の共感を得られる内容を考えても、実際に動画を見てもらえなければ、視聴者にメッセージを届けることはできません。
視聴者の興味・関心をひくためには、動画に「ストーリー性を持たせる」ことが重要です。説明や解説のみを行っている動画よりもアニメや映画のようにストーリーを意識した動画のほうが視聴者は感情移入しやすくなります。
ブランディング動画には、自社のコンセプトやサービスを伝えるためにも「ストーリー性」を意識することが大切です。
ブランディング動画の活用シーンって?
ブランディング動画を制作する目的を把握できたところで、制作した動画は実際にどのような場面で活用できるのでしょうか。費用をかけてブランディング動画を制作しても、多くの人に見てもらえなければ大きな効果は得られません。
ここからは、制作したブランディング動画をどのように活用できるのか、3つのケースについて紹介します。
テレビCMや自社ホームページ、SNSなど
まず、テレビCMや自社ホームページ、SNSなどに活用するケースです。年齢層や性別などに限らず多くの人に見てもらえるため、ブランディング動画を最も広く周知できる方法といえるでしょう。
特にSNSは、動画を見た人がすぐに感想を書いたり拡散したりするなど、リアルタイムな動きが多く、話題になればさまざまな人にリーチできるでしょう。会社のイメージアップにも繋がりやすく、売り上げや顧客増加も期待できます。
イベント、IR活動など
イベントやIR活動などで活用するケースでは、短時間で自社の魅力を伝えられるというメリットがあります。これらのイベントに参加しているユーザーは、もともと自社に対して興味を持っていることが多いため、動画を見てもらえれば成果に繋がりやすいといえるでしょう。投資家へのアピールにもなり、新たなファンの獲得にも繋がります。
インナーブランディングや採用活動
最後に、インナーブランディングや採用活動などで活用するケースです。企業概念や商品・サービスの特徴など、情報量の多い内容でも動画であればアニメーションなどの技術を使って表現できるため、短時間で理解しやすいメリットがあります。
動画であれば、文章では理解しにくい複雑な説明でも、映像やナレーションを入れることで効率的に説明できます。
ブランディング動画制作の費用相場
ブランディング動画制作には、次のような費用がかかります。
- 人件費(スタッフ・役者)
- 企画費(スケジュール作成・台本作成・キャスト選定等)
- 諸経費(撮影機費・美術制作費・交通費・宿泊費・スタジオ利用料等)
トータルの費用は動画の内容や制作時間によって異なり、10~300万円程度と大きな幅があります。さらに、有名な俳優の起用や高度なCG、特別なロケーションなどこだわって作成と、費用が300万円を超す場合もあります。
ブランディング動画制作を外注するメリット
専門業者へのブランディング動画制作の外注は次のようなメリットがあります。
- 品質が高い
プロの映像制作会社は、視覚的・感情的に魅力的な映像を作る専門知識と技術を持っています。高度な撮影機材や編集ソフトを活用し、自社制作では難しいクオリティを実現できます。
- 効率的な制作
制作会社は企画、撮影、編集まで一貫して対応し、プロジェクトを効率的に進行します。自社での試行錯誤を省き、スムーズに高品質な動画を完成させることが可能です。
- 客観的な視点
自社制作では自分たちの視点に偏りがちですが、外注することで第三者のプロ視点を取り入れ、ターゲットにより効果的に響く動画が作れます。
- リソースの節約
動画制作には多大な時間と労力がかかるため、外注することで自社のリソースを他の重要業務に集中させられます。
ブランディング動画は、映像制作スキルのある人材と撮影機材があれば費用を抑えて自社制作することも可能です。しかし、上に挙げたメリットがあることから、外注はブランド価値向上を目指すうえで効果的な選択肢といえます。
ブランディング動画制作の外注先の選び方
ブランディング動画制作の外注先を選ぶ際には、以下のポイントに注目することが重要です。
- 制作実績
自社のイメージやターゲットに合ったスタイルで動画を作れるかを見極めるため、過去の制作実績を確認します。
- 企画力や理解力
ブランドの価値や理念を深く理解し、それを的確に表現する企画力があるかを確認します。ヒアリングを通して自社の意図をくみ取ったうえで、どのように映像に落とし込むかが大切です。
- コミュニケーション力
スムーズに動画作成をおこなうには、コミュニケーション力も重要です。特に初めて動画制作を依頼する場合は、動画制作の流れや料金体系など初歩的なことから丁寧に説明してくれるか確認します。
- コストと納期
予算内で希望するクオリティを実現できるか、納期に間に合う体制が整っているかを事前に確認します。
- アフターサポート
ブランディング動画は作って終わりではなく、公開して成果を出すのが目的です。活用方法のアドバイスが受けられるかや納品後の修正に対応してもらえるかなども事前に確認しておくことが大切です。
これらを総合的に判断して、自社の目的に合った外注先を選びましょう。
ブランディング動画の制作事例5選
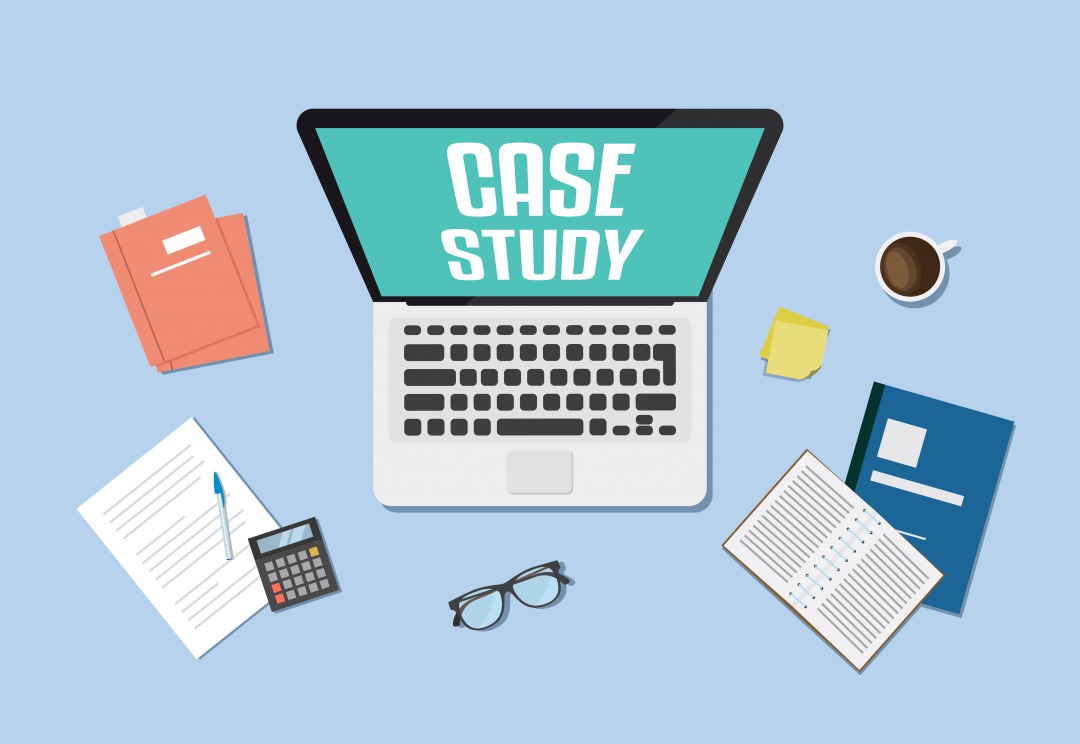
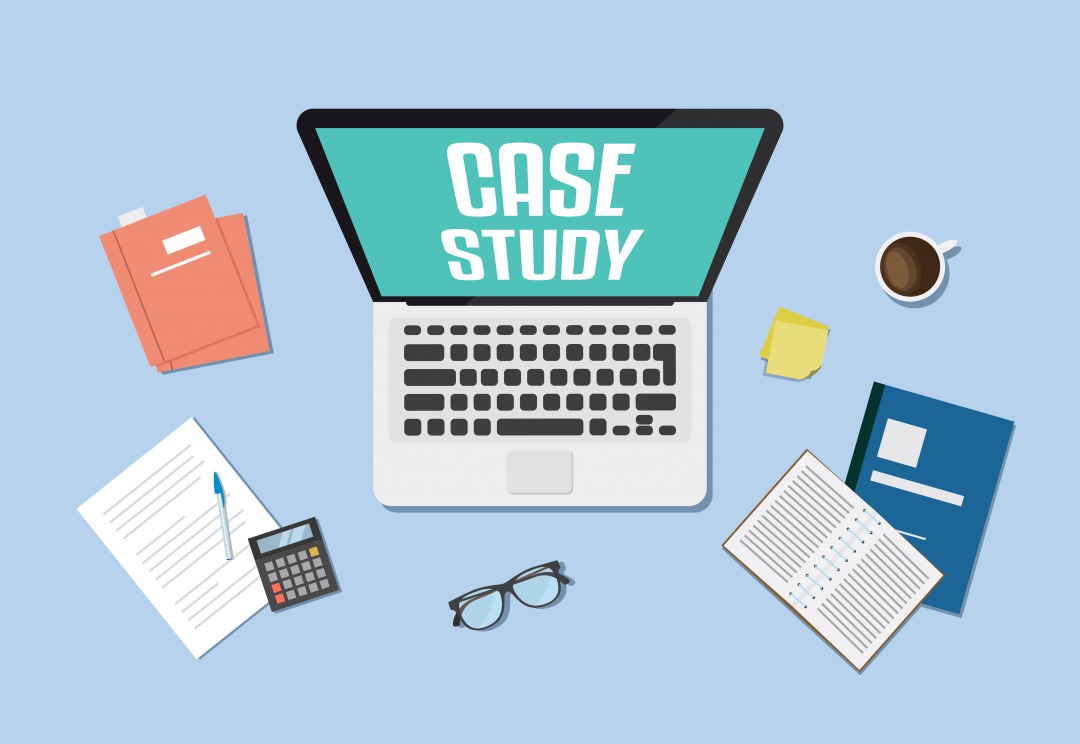
ブランディング動画の制作に取り組む企業が増えていますが、ブランディング動画を正しく理解している人は多くありません。ここでは、ブランディング動画を数多く制作してきた弊社ブルークスの動画制作事例をご紹介します。
事例①実写動画によるブランディング:オートリブ株式会社様
オートリブ株式会社様は、自動車を含むモビリティの安全ソリューションを開発・生産・販売しています。ブランディング動画では、安全で持続可能なモビリティ社会を目指して真摯に取り組む様子を実写で描きました。
動画は社長や社員のインタビューを中心に構成し、最新技術や製品、安全性向上への取り組みを強調しました。また、同社のグローバルな展開や各地域での活動についても触れるとともに、企業理念、ビジョン、安全性へのコミットメントも紹介しています。
実際の工場内の映像、壮大で力強い音楽、そして説得力のあるナレーションが一体となり、見る人に「未来の安全を共に創る」というメッセージを強く伝える映像に仕上げました。
事例②アニメーションによるブランディング:タクトホーム株式会社様
タクトホーム株式会社様では、戸建て・マンション分譲をはじめ、不動産関連事業を行っています。
タクトホームのブランディング動画は、営業や施工などチームが一丸となって家づくりに取り組む様子をアニメーションで表現しています。キャラクターを登場させてストーリー性を持たせるとともに、疾走感のある音楽を組み合わせ、会社紹介や事業内容をコンパクトにまとめました。
事例③SDGsブランディング:日本航空様
日本航空様では、CSR活動をブランディングの主軸において動画を制作しています。「アイソメトリック」という3Dに近い立体的なアニメーションの手法を用いて視聴しやすい動画にしているのが特徴です。
近年CSR活動やSDGs活動は世界の関心事の一つであり、CSR活動SDGsを啓蒙しながら日本航空のブランディングも行うことができます。
特にマスメディアでもSDGsへの取り組みは大きくなっており、ブランディング動画として効果的に宣伝をしていること、そして企業の役割であるCSR活動を行っているというブランディングの好例となっています。
SDGsのブランディング動画を制作すると経済産業省から補助金が出ることがあるため、SDGsと絡めたブランディング動画は今後も増えていくことが予想されます。
事例④企業紹介ブランディング:東北電力株式会社様
東北電力株式会社様は、2011年3月に起こった東日本大震災の被害をとらえながら、停電によって失われた光を取り戻すストーリーを動画にしました。多くの職員が現場で奮闘している姿を映し、復活した光に人々が集う様子が幻想的な音楽とともにセンセーショナルに描かれています。
2021年に東日本大震災の発生から10年という節目を迎えたため、グループ全体の企業姿勢を訴求するために制作されました。
事例⑤インナーブランディング:アイアグリ株式会社様
アイアグリ株式会社様のインナーブランディング動画は、視聴後に社員の自己肯定感を高め、自社で頑張ろうと思えるような内容になるよう、BGMやテロップにも工夫を凝らして制作しています。
各事業部で働く社員の姿を撮影し、エモーショナルなコピーを加えることで、異なる部署の社員が共通の目標に向かって努力している姿を表現しています。社員同士の一体感を育み、組織の結束を強める映像に仕上げました。
効果的なブランディング動画制作をお求めならプルークスへご相談を
ブランディング動画の基本的な内容やメリット、具体的な制作事例を紹介しました。一貫性のあるメッセージを持ったブランディング動画を制作し、視聴者の共感を得られれば、間接的ではありますが大きなメリットが期待できます。
SDGs/CSRに取り組んでいる企業であれば、それを訴求することで相乗効果が得られるでしょう。ブランディング動画は自社で制作することもできますが、より効果的に伝えるためには動画制作会社に依頼することがおすすめです。
弊社プルークスは、豊富な制作実績と多彩な演出ノウハウを持っているため、お客様のご要望に合わせた動画制作が可能です。また、映像制作後の露出媒体や出稿先のご相談も受け付けておりますので、より良いブランディング動画制作をお求めでしたら、ぜひプルークスまでご相談ください。
ブランディング動画に関してよくあるQ&A
ブランディング動画に関する、よくある質問について回答します。
Q. ブランディングの意味は?
A. 企業価値を向上するための活動です。
単に商品やサービスを一方的に紹介するだけのプロモーションとは異なり、自社の活動を見た・聞いた人に共感してもらい、ファンになってもらうことが大きな目的です。ファンが増えれば商品や社名がブランドとして確立され、売り上げアップや口コミなどによる拡散など、さまざまな効果が期待できます。
Q. ブランディング動画はどんなシーンで使える?
A. 自社ホームページやイベント開催時、採用活動・説明会など、さまざまなシーンで活用できます。
一度動画を制作しておけばさまざまな場面で使いまわすことができるため、一概に制作するコストが高いとはいえません。
Q. ブランディング動画の制作費用はいくら?
A. 動画の尺(長さ)やどのような演出方法を取り入れるかによって価格は大きく変動しますが、300万円~制作できます。
動画制作時のコストを抑える方法として、動画に出演するキャストを自社で用意する、人を出演させるのではなくアニメーションにする、素材を用意するなどの方法が挙げられます。プルークスでは、ご予算に合わせて演出案や最適な制作体制を提案しておりますのでお気軽にお問い合わせください。